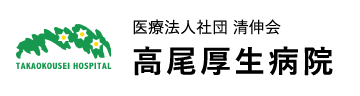- 名称
-
医療法人社団 清伸会
高尾厚生病院 - 所在地
-
〒193-0846
東京都八王子市南浅川町3815 - 連絡先
-
Tel: 042-661-0316
Fax: 042-662-9850 - 総病床数
- 精神一般病棟:80床
- 病床内訳
-
開放病床:0床
閉鎖病床:80床 - 診療科目
- 精神科、内科、歯科
- 代表者
- (理事長)朝倉 清
- 施設基準
-
基本診療料
-
[精神入院]
精神病棟入院基本料
精神病棟入院基本料とは?
精神科病院に入院した際に、病院側に支払われる診療報酬の一部です。これは、患者さんが入院中に受ける様々な医療サービスの費用を包括的に評価したもので、いわば「入院にかかる基本料金」のようなものです。
対象となる医療サービス
この基本料には、以下のような医療サービスが含まれています。
- 医師による診察、治療、投薬管理
- 看護師によるケア(日常生活の援助、症状観察など)
- 精神療法(集団療法、作業療法、個別療法など)
- 食事、居住の提供
- 入院中の医学管理
入院料のランクと医療提供体制
精神病棟入院基本料には、IからVまでの5つのランクがあります。ランクが高いほど、手厚い医療体制が整っていることを示します。つまり、より多くのスタッフが配置され、専門的な治療やリハビリテーションが提供されます。
ランクの違いは、例えば以下のような点で現れます。- 看護師の配置人数:ランクが高いほど、患者さん一人あたりに配置される看護師の人数が増えます。
- 精神科医師の配置人数:同様に、医師の数もランクによって異なります。
- 提供される治療プログラムの種類や頻度: 高いランクの病棟では、より多様なプログラムが提供され、個々の患者さんのニーズに合わせたきめ細やかなケアが受けられます。
- リハビリテーションの充実度:社会復帰支援に向けたリハビリテーションも、ランクが高いほど充実しています。
自己負担額への影響
基本料のランクが高いほど、入院費用も高くなります。ただし、健康保険が適用されるため、患者さんの自己負担額は一定の割合に抑えられます。高額療養費制度を利用すれば、自己負担額がさらに軽減される場合もあります。
まとめ
精神病棟入院基本料は、入院中の医療サービス全体を評価したもので、そのランクによって医療体制の充実度が異なります。どのランクの病棟が適切かは、患者さんの症状やニーズによって判断されます。入院前に医師や医療相談員とよく相談し、最適な医療環境を選ぶことが大切です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[看補]
看護補助加算
看護補助加算とは?
病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。
看護補助者の役割
看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。
- 食事の介助
- 排泄の介助
- 入浴の介助
- 移動の介助
- 身の回りの整理整頓
- 体位交換の補助
- 清潔保持の補助
これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。
看護補助加算のメリット
看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。
- きめ細やかなケアを受けられる:看護師がより専門的な業務に集中できるため、看護補助者が患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを提供できます。
- 日常生活のサポートが充実する:食事、排泄、入浴など、日常生活における様々な場面でサポートを受けられます。
- 入院生活の負担軽減:看護補助者のサポートにより、入院中の身体的・精神的負担を軽減できます。
加算の要件
この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。
まとめ
看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
特掲診療料
-
[精]
精神科作業療法
精神科作業療法とは?
精神科作業療法は、精神疾患のある方が、日常生活や社会生活を送る上で困っていることを改善するためのリハビリテーションです。作業活動を通して、心身の機能回復や維持、生活 skills の向上を目指します。
どんなことをするの?
様々な作業活動を通して、下記のような能力の向上を目指します。
- 日常生活能力の向上:
着替え、食事、入浴、掃除、洗濯など、日常生活に必要な動作をスムーズに行えるように練習します。 - 社会生活 skills の向上:
コミュニケーション skills、対人関係 skills、金銭管理、公共交通機関の利用など、社会で生活していくために必要な skills を身につけます。 - 集中力・持続力の向上:
作業に集中して取り組むことで、集中力や持続力を高めます。 - 意欲・自信の向上:
作業を達成することで、意欲や自信の回復を促します。 - ストレス対処 skills の向上:
ストレスを軽減し、うまく対処するための skills を身につけます。
どんな作業をするの?
作業療法で行う作業活動は、個々の症状や目標に合わせて様々です。例えば:
- 創作活動:絵画、陶芸、手芸、音楽など
- 園芸:植物の栽培、収穫
- 料理:調理、盛り付け
- レクリエーション:ゲーム、スポーツ
- 日常生活動作訓練:着替え、食事、入浴の練習
- 社会生活 skills 訓練:模擬店、職場体験
「施設基準の特掲診療料」って?
「施設基準の特掲診療料」とは、質の高い医療を提供している医療機関に対して、国が定めた基準を満たしている場合に支払われる診療報酬のことです。「精神科作業療法」においても、一定の基準を満たした医療機関で、より専門的な作業療法を受けることができます。具体的には、作業療法士の人員配置や設備などが基準として定められています。この基準を満たしている医療機関で作業療法を受けることで、より効果的なリハビリテーションを受けることが期待できます。
どこで受けられるの?
精神科病院や精神科クリニックなどで、作業療法士が常勤している医療機関で受けることができます。「精神科作業療法」の施設基準を満たしている医療機関は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 日常生活能力の向上:
-
[外在ベⅠ]
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
どんな医療機関が対象?
病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。
どんな基準があるの?
主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」と「多職種連携の推進」に関する基準があります。
- 質の高い医療の提供体制
- 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
- 医療安全対策の実施
- 感染症対策の実施
- 在宅医療の充実
- 多職種連携の推進
- 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
- 地域包括ケアシステムへの貢献
- 他医療機関との連携
この評価料で何が変わるの?
この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。
- より安全で安心な医療を受けられる
- 多職種によるチーム医療を受けられる
- 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる
つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 質の高い医療の提供体制
-
[入ベ14]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
なぜ必要なの?
医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。
評価のポイント
入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。
具体例
- 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。
- 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。
- 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
私たちにとってのメリット
入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。
最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
その他
-
[175]
薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名等の記載を省略する届出
薬剤料の記載簡略化について
病院や診療所では、患者さんに医療費の内訳を明細書で説明する義務があります。通常、薬剤料については、使用した薬剤ごとに薬価などを記載しています。しかし、ある一定の条件を満たす薬剤については、個別の記載を省略できる場合があります。このページでは、その条件と、それが患者さんにとってどのような意味を持つのかを解説します。
薬価が175円以下の薬剤の記載省略
医療機関は、「薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名等の記載を省略する届出」を行うことができます。これは、厚生労働省が定めた施設基準に基づく届出です。この届出を行った医療機関では、1単位あたりの薬価が175円以下の薬剤については、明細書に個別の薬剤名などを記載せず、「内用薬」や「外用薬」といったようにまとめて記載することが認められています。
例えば、風邪薬などで使用される一般的な薬剤の中には、1単位あたりの薬価が175円以下のものが多くあります。これらの薬剤を複数使用した場合、従来はそれぞれの薬剤名や薬価を明細書に記載していましたが、この届出を行うことで、まとめて「内用薬」と記載することが可能になります。
この届出によるメリット・デメリット
この届出には、患者さんにとってメリットとデメリットがあります。
メリット
- 明細書が見やすくなる:薬剤ごとに細かく記載されていたものがまとめられるため、明細書全体が見やすくなります。
デメリット
- 使用された薬剤の詳細が分かりにくくなる:個別の薬剤名が記載されないため、どのような薬剤が使用されたのかが分かりにくくなります。もし、使用された薬剤について詳しく知りたい場合は、医療機関に問い合わせる必要があります。
患者さんへの影響
この届出は、薬剤の価格や使用量に影響を与えるものではありません。薬剤料の総額は変わりません。変わるのは明細書の記載方法のみです。つまり、支払う金額が増えるというわけではありません。
医療機関がこの届出を行っているかどうかは、明細書を確認するか、医療機関に直接問い合わせることで確認できます。
もし、明細書の記載について不明な点があれば、遠慮なく医療機関のスタッフにお尋ねください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[酸単]
酸素の購入価格の届出
酸素の購入価格の届出とは?
医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。
なぜ届出が必要なの?
酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。
誰が、いつ届出するの?
酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。
届出しないとどうなるの?
届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。
私たちへの影響は?
この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。
まとめ
- 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
- 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
- 医療機関は毎年1回届出が必要
- 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[食]
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?
入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。
これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。
食事療養(Ⅰ)とは
食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 患者さんの病状に合わせた食事を提供
(糖尿病食、腎臓病食など) - 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
- 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
- 定期的な栄養状態の評価
生活療養(Ⅰ)とは
生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 入院生活における相談窓口の設置
- 療養生活上の助言や指導
- 社会福祉士等による相談支援
- アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備
つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 患者さんの病状に合わせた食事を提供
-
[精神入院]
精神病棟入院基本料
病院概要
病院理念
最も弱き人のために
基本方針
- 法令順守
- 患者本位
- 自己研鑽
医療連携
当病院は、患者様に次のような必要性が生じた場合、医師の判断により、患者様の症状に応じた早期の対応を図ります。
- 緊急もしくは早期の入院治療の必要が生じた場合
- MRIやCT等をはじめとする精密検査の必要が生じた場合
- 専門医による外来治療の必要が生じた場合
連携病院
- 東京医科大学八王子医療センター
- 南多摩病院
- 東海大学八王子病院
八王子市医療連携登録医制度
登録番号: 八医連第0310号
行動計画
当病院は、社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、妊娠・出産・復職時における支援に取り組むため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2021年8月1日 ~ 2026年7月31日までの5年間
2.内容
目標1: 妊娠、育児に係る社内制度を職員に周知して、理解の促進をはかる。
<対策>
- 2021年8月~ 妊娠、育児に係る社内制度の内容を全職員に周知、説明する。
目標2: 円滑な職場復帰を支援するために、育児休業を取得する職員に対し、復帰前と復帰後に面談を行う。
<対策>
- 2021年8月~ 育休復帰支援のための面談の内容を検討する。
- 2021年8月~ 職場復帰に向けての面談制度の実施をする旨を職員に周知する。